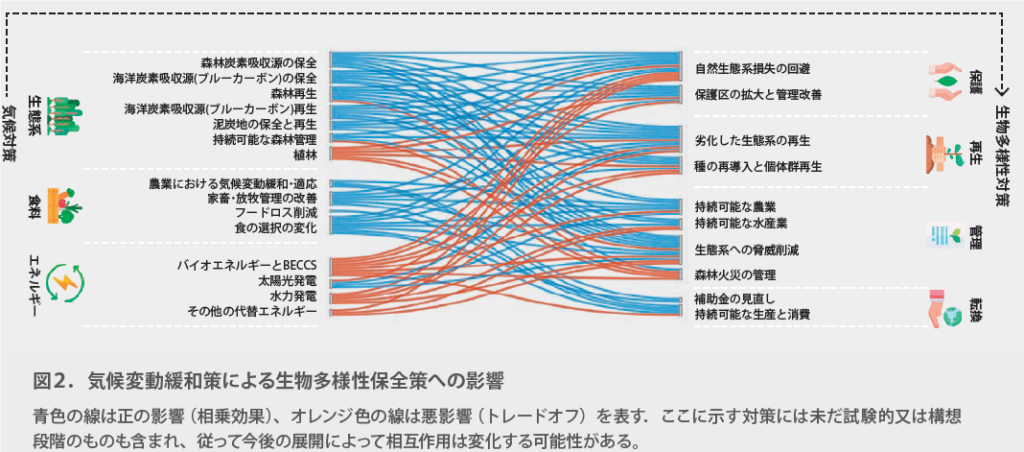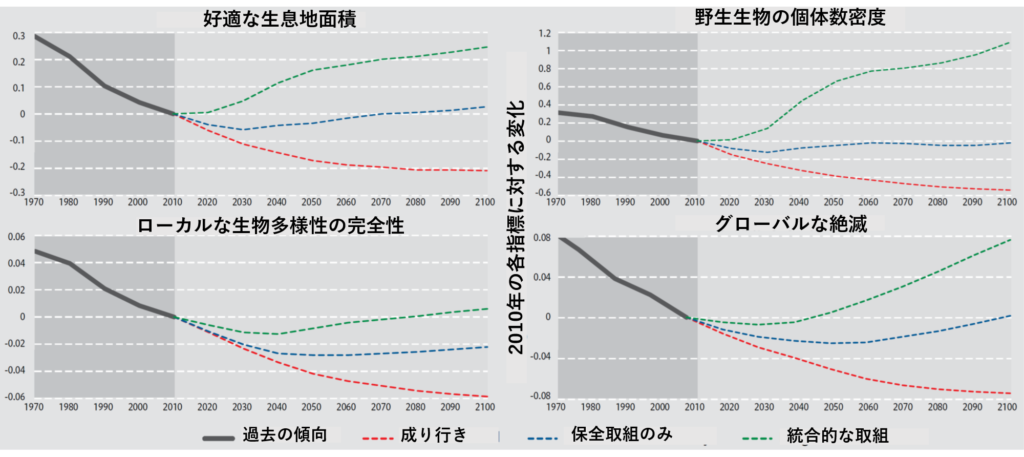近年、リジェネレーションという概念が欧米で注目を集めています。リジェレーションとは、現在の状態で地球環境を持続させるのではなく、生態系を現状よりも再生/復元させ、その恵みを高めることで様々な社会課題の解決に結びつけるという考え方です。「また新しい言葉が出てきた」と感じてしまいますが、日本では自然を活かすリジェネレーションの知恵が受け継がれてきました。里山の知恵です。今回は、里山を事例にリジェネレーションを考えます。
里山は、地域によってさまざまな異なる景観を見せますが、特徴はいずれも、畑や水田、屋敷地、鎮守の杜など、人の手が加わった自然がモザイクのように入り組んだ景観になっていることです。里山の農地で行われてきた伝統的農業は、化学肥料や農薬を使う慣行農業と異なり、土壌など自然の力を活かして土地の生産力を再生させ、農業を営んできました。
低地の里山として、江戸時代に作られた三富新田(さんとめしんでん)を取り上げましょう。この新田は、現在の埼玉県入間郡三芳町の上富(かみとめ)地区、所沢市の中富(なかとみ)・下富(しもとみ)地区に位置し、それぞれ共通する富の文字をとって三富(さんとめ)と呼ばれました。三富新田の開拓では、藪状になっていた荒地を、ヤマと呼ばれた農用林(平地林)、耕作地、屋敷地の三か所の合計面積が5町歩(約5ha)ずつ区分できるように均等に分与されました。今でいう環境設計のゾーニングです。そのうち、屋敷地は作業場や母屋として5反(約0.5ha)、畑は一軒あたり2町5反(約2.5ha)、痩せた土地を落ち葉の堆肥で補うために農用林も2町5反(約2.5ha)が確保されました。
三富新田では、貧栄養に強く、萌芽再生力が強いコナラやクヌギ、シデ類、エゴノキ、アオハダなどの落葉広葉樹が農用林として植栽され、管理されています。農家は、ケヤキやアカマツで構成される屋敷林で家屋の立て直し材料を、農用林の間伐材からは薪などの燃料やシイタケのほだ木を得ています。そして農用林から集められた落ち葉は、家畜や家禽の糞が混ぜられて堆肥とされ、そこに薪の灰も加えることで、土づくりが今でも行われています。その畑では、地域特産の富のイモ(サツマイモ)やサトイモ、ホウレンソウなどの野菜が生産されます。出荷した残りの野菜くずも廃棄物にはしません。家畜や家禽の餌としたり、畑の肥料として使われます。
このように三富新田の里山には、農家が自然の恵みを高めるために、自然資源を循環利用し、廃棄物を出さない知恵が見られます。これはサーキュラーエコノミーを実現したシステムであり、里山は循環型社会のロールモデルといえます。また有機物を利用した土づくりは土中の炭素貯留量を高めます。米国で盛んになりつつあるリジェネラティブ農業は、里山の伝統的農業では当たり前のように行われていたものです。
この三富新田には、農家の営みとかかわりを持つ特有の生態系が存在しています。毎年の下草刈りや落ち葉掃きにより、微生物が活発になった土壌では、春にはイチリンソウやスミレの花が咲き、秋にはリンドウや野ギクの花が咲きます。花に訪れるハナバチも多様な種がいて、野菜の受粉を担っています。農用林では、鳥類やタヌキ、野ネズミなどの小動物が生息し、樹林の果実を食べて種子を運び、木々の発芽の機会を生み出しています。露地栽培のサツマイモ畑では、昼間はヒバリやハクセキレイなどの鳥が畑の害虫を捕らえ、夜には、屋敷林にすむアブラコウモリの群れが畑地に飛来し、野菜害虫となる蛾類を捕らえ、天敵としての役割を果たしています。
在来種を利用した受粉媒介や統合的な害虫管理(IPM)といった、農業生物多様性を活用する持続的な農業システムが里山に見られます。

次は、山形県鶴岡市の温海(あつみ)地区を例に、山地の里山で行われる「焼き畑農法」を紹介します。温海地区は、江戸時代から杉の伐採地を利用して、焼き畑で赤かぶの栽培を行ってきた集落です。赤かぶの焼き畑では、山に火を入れることで地中の病害虫発生を抑制するとともに、杉を伐採した際に出た枝葉の灰が天然肥料になります。赤かぶ栽培で土の栄養が減った翌年には、やせ地でも育つ蕎麦や豆を育て、最後には若い杉を植林します。次に同じ場所で焼き畑をするのは、杉が樹齢約50年に育ってからで、材を収穫できるとともに、その頃には土の栄養も回復しています。
このように温海地区の焼き畑農業は、農業と林業を組み合わせ、自然の力を活かした土づくりを設計に組み込んだ、持続的な農林業システムといえます。
なお温海地区では、赤かぶ栽培のほかに、シナノキという樹木の樹皮をはぎ、灰汁で煮て乾燥させたものから糸を紡いだ「しな織り」、灰汁であく抜きして日持ち良くした「笹巻き」など、焼き畑により発生した灰を利用した農産物や加工品も販売されています。間伐材は日々の暮らしの薪としても利用されます。このように焼き畑農法に基づく生活の知恵は、地域の産業を支え、自然環境を維持し、そして文化的価値までも生み出しています。
日本各地の里山は、数十年ほど前から、管理が放棄されて藪になってしまうことが問題視されてきました。里山の荒廃は農林業の衰退だけでなく、土砂流出や洪水制御といった災害の発生にもつながることが危惧されています。このような、里山の自然が持つ国土保全の機能は「グリーンインフラ」と称され、新たな価値として注目されはじめています。水田を活用して地下水の涵養や雨水流の流出制御を促進する、森林管理によって生態系を健全に保ちCO2吸収や土砂崩壊防止機能を高めるなど、緑のインフラを活かした防災・減災の場として、里山の自然が見直されています。
これからの企業の生物多様性活動にはネイチャーポジティブの視点が求められます。里山の知恵にならい、たとえばサプライチェーンでの農業や林業といった生産システムをリジェネラティブに変革する事は、ポジティブを拡大するための重要な手法の一つです。自社事業をネイチャーポジティブに変革するために、温故知新の視点をもって里山の知恵に学び、日本版リジェネレーションを考えてみてはいかがでしょうか。
(永石文明)
.png)